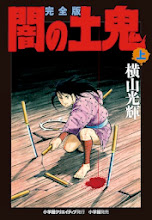昨年末、阿久悠さんの作品集が二タイトル発売された。「こどもへの阿久悠 かつてこどもだったあなたへ、そしてそのこどもたちへ」「おとなへの阿久悠 酒場で聴きたい名歌たち」がそれだ。 前者は「宇宙戦艦ヤマト」や「ウルトラマンタロウ」を始めとする、こども番組の主題歌や各種企画盤に収録された楽曲を集めたもので、自宅の愛猫の性格と日常を描いた未発表の詩「うちのニャンコは大先生」が、新曲として収録されている。一方、後者は「北の宿から」「五番街のマリーへ」「舟歌」など、カラオケの定番曲、いわば文字通りの〈名歌〉が集められたもので、曲名を見ただけでメロディと歌詞が浮かぶヒット曲が満載である。 ジャケットには、和田誠さん作画による阿久さんの
ポートレイトが採用されているが、どうにも見覚えがないので、その旨を和田さんに訊ねると、「以前、プライベートな会のために描いたら、それを阿久さんが気に入ってくれたらしくて、その後、原画を差し上げたんだよ」とのこと。和田さんは阿久さんとふたりで歌謡曲についての対談集「A面B面 作詞・レコード・日本人」を著していることもあって、仕事を離れても親交があったようだ。実に親しみやすいジャケットに仕上がっていると思う。 私は生前の阿久さんに、二度、お目にかかったことがある。監修を務める音楽ドキュメンタリー番組で、阿久さん、そして阿久さんとのコンビで数多くのヒット曲を作った作曲家の都倉俊一さんに出演していただくことになり、事前の打ち合わせで六本木の事務所に
お邪魔したのが最初で、二度目が本番収録のスタジオである。 幼少時にテレビで見たオーディション番組での険しい表情が刷り込まれているから、初対面の際には緊張した面持ちで臨んだのだが、それを察したのか、阿久さんのほうから気さくに話しかけて下さり、素朴な疑問にも嫌な顔ひとつ見せることなく、懇切丁寧に答えて頂いた。あれはCMソングの話だったろうか。こちらの質問に対して、述懐しながら、時折り、はにかんだように笑顔を見せられたのが印象的だった。 また、本番収録の現場でトラブルがあり、一瞬その場が凍り付いた時も、阿久さんはスタジオの隅で、ただ黙って腕組みしながら泰然として撮影再開を待ち、おろおろするスタッフに「こんなこともあるさ」と
いったふうに、一文字に結んだ唇の端を上げて応えていた。あの時の懐の深さと存在感が忘れられない。 阿久さんが亡くなったのはそれからおよそ二年後のこと。結局、三たびお目にかかる機会は訪れなかったが、わずかながらに交わした会話はどれも印象深いことばかり。直接交わした言葉は少ないが、歌を通して胸に染み込んだ言葉は数えきれない。この二枚のアルバムに収録された楽曲はほとんどそらで歌えるものばかりだが、歌詞カードを見ながら聴くと、より一層その言葉の重みと深さが感じられる。 (濱田高志=アンソロジスト) ーーーーーーーーーーーー ●「こどもへの阿久悠」「おとなへの阿久悠 」各2800円+税/日本コロムビアより発売中

この発表はまだ言えない。言わないようにしよう。でも、誰かに言いたくてずっとムズムズしていた。先に言います。『KIKI RECORD』の看板デザイン、コースター、レコードのヴィニール袋のデザインは宇野亜喜良さんです。きっかけはこの「週刊てりとりぃ」の編集長、濱田高志さん。あの一言がなければ
実現できなかった。 以前「月刊てりとりぃ」にも書いたが、宇野さんの絵はぼくが小学4年生のころ、姉の部屋に飾ってあった寺山修司のポスターを見てはじめて出会った。それ以来ずっとあこがれの人だった。その方にデザインを頼むのだから。 去年、9月にオープンする予定だった鷹の台の喫茶
店『KIKI RECORD』はオープンの直前になって開店することができなくなった。レコード棚の寸法を間違えたこともあるけど、自分が納得する形でお店を開店させたかった。まだ始めてはいけないような気がした。 コーヒーは岐阜のお店『OPUS』で教えていただいた。ここのコーヒーはとてもおいしくて、初めて飲んだとき驚いた。そこでぜひ、ここと同じコーヒーを東京でも出したいと思ったのだ。ホットサンドの指導には中目黒にあった『プラッタ』の赤岩さんにしていただいた。いろいろなホットサンドを作り、そこから店長、スタッフとメニューを考えた。内装にはビンテージを扱う家具屋さん『SALLYS』の北之園さん。北から南まで、お店に合う家具を探してもらい、

内装の工事まで面倒見ていただいた。佐藤さん、赤岩さん、北之園さん、本当にお世話になりました。 鷹の台というところはぼくが育ったところだった。東京なのに東京ではないような雰囲気のある場所。国分寺から西武国分寺線に乗って2駅。東村山からも2駅。駅から歩いて2分のところに『KIKI RECORD』があります。改札を出て左、線路沿いに歩き、一つ目の道を右に曲がってすぐ。
最初のオープン予定日から半年も経ってしまいましたが、その間、いただいたアドヴァイスは本当に嬉しかったです。 オープンは4月の第一日曜日、6日。午前11時から午後8時まで。お休みは、月曜日と木曜日。お待たせしてしまい、本当に申し訳ありませんでした。オープンの日はぼくもお店に立ちます。ぜひ、遊びに来てください。 (馬場正道=渉猟家)
|
長崎学のススメ 『ドラム事始め』

時は明治。アメリカに留学していた八弥青年は、大統領選挙のパレードに遭遇します。何を思ったのか八弥くん、マーチング・バンドに飛び入り参加。見事にドラムをたたきこなしたそうな。驚きです。僅か数年前までチョンマゲをしていた日本人が、ロールなどのドラミング・テクニックを習得していたということですから。 日本人が最初にドラムに出逢ったのは、八弥くんが
パレードに参加する二十数年前、幕末期の長崎。私が営む雑貨店から徒歩10秒の場所にあった海軍伝習所(現・長崎県庁)でのことです。指導したのはル・イ・ヘフティというオランダ人。当初、生徒は3人でしたが「私も学びたい」という者が続出、先生は3人に増員されました。日本人は何故これほどドラム習得に熱心だったのでしょうか。洋楽に魅了されたとかそういう理由ではありませんよ。
軍事技術として必須だったからです。武器が「刀」から「銃」に変わり、個人戦でチャンチャンバラバラとやる時代は終わりました。上官の命令で、軍隊が一斉に「進んで」「止まって」「並んで」「撃つ」ことができなければ戦えません。そんな時「号令」だと離れた兵隊に聞こえない恐れがあります。ところが「ドラム」であれば遠くまで、しかも正確に命令が届くというわけです。 こうしてドラミングを学んだ各藩のドラマーたちは地元へ帰り、その技術を後輩たちに伝達していきました。高遠藩士だった八弥くんも、長崎帰りの先達からこの軍事技術を伝授されたのです。明治になると文部省の官僚になり、西洋の進んだ教育を日本に導入するためアメリカに研修留学。日本に戻り、留学先で知り

合ったアメリカの音楽教育者メーソンと共同で『蛍の光(スコットランド)』「蝶々(スペイン)」「仰げば尊し(アメリカ)」といった、洋楽民謡の日本語カバーを収録した『小学唱歌集』を編纂することになります。八弥くんとは、日本音楽近代化のフロンティア伊澤修二その人です。 (高浪高彰=長崎雑貨たてまつる店主) ーーーーーーーーーーーー ●『国家と音楽 伊澤修二がめざした日本近代』奥中康人・著(2008年/春秋社・刊)東京芸術大学音楽学部の創設者・伊澤修二の生涯を通して、国家形成に果たす音楽の役割を考える1冊。
|
|